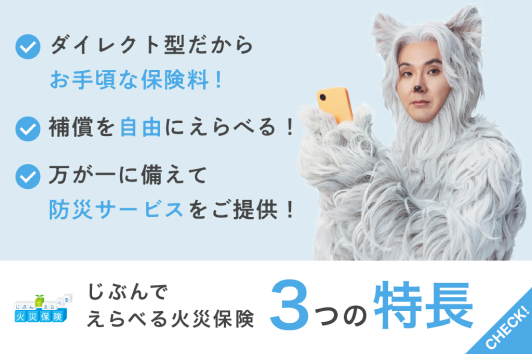火災保険ガイド
火災保険で放火の損害は補償される?適用条件や保険金が出ないケースを解説
最終更新日:2023/5/10

火災保険は、放火による損害も原則として補償されます。しかし、放火は第三者の故意による犯罪行為です。そのため、補償されるか判断が分かれることもあり、場合によっては保険金を受け取れないケースもあります。
本記事では、火災保険で放火の損害が補償されるケース、されないケースについて詳しく解説します。
放火による火災の発生件数
2022年(1~9月)の総務省消防庁発表によると、全国で発生した火災27,432件のうち、放火および放火の疑いを原因とする火災件数は2,662件と、全体の約10%を占めています(※1)。
消防庁が発表する2021年から過去5年の発生件数のデータによると、放火は2017年の3,528件から2021年の2,333件へ、放火の疑いは2017年の2,305件から2021年の1,555件へと減少傾向であることがわかります(※2)。しかし、火災全体の件数が減少傾向であるため、全体の約10%という割合はほとんど変わっていません。
また、放火および放火の疑いにおいて注視したいのが損害額の大きさです。2021年の放火による火災の損害額は約67億円、放火の疑いによる火災の損害額は約262億円と、住宅火災の原因で上位にあるコンロ(約28億円)、たばこ(約37億円)、電気ストーブ(約42億円)に比べると損害額の大きさが浮き彫りとなっています(※2)。
- ※1
-
出典:総務省消防庁「令和4年(1月~9月)における火災の概要(概数)について」
- ※2
-
出典:総務省消防庁「令和4年版 消防白書」
放火による損害は火災保険が適用される?
第三者の放火による損害は、原則として火災保険の補償の対象になります。
放火は放火犯の故意により起こるものであり、住宅の契約者が注意を払っても避けきれない偶発的な事故という扱いです。そのため、原則としてほかの火災と同じように保険金を受け取れます。
放火によるもらい火も補償対象
放火が原因のもらい火は延焼損害とみなされ、ご自身が加入する火災保険の補償が適用されます。
放火犯の故意による火災であるため、自宅ではなく隣家が失火元であっても、過失責任のない隣家には「失火責任法」により賠償請求できません。失火責任法とは、隣家からの出火によりご自身の住宅が被害を被っても、重大な過失がなければ原則として失火者に対して損害賠償責任を問えない法律です。
一方で、放火は故意による犯罪であるため、加害者である放火犯に対して損害賠償請求が可能です。ただし、加害者との示談が成立しなかった場合は、自ら民事訴訟を提起するなどの手続きをとらなければ賠償は受けられません。
放火による損害で補償が受けられないケース
火災保険は、保険会社の定める免責事由に該当する場合は補償が受けられません。免責事由とは、保険会社が定める保険金を支払わないケースのことです。
免責事由は各保険会社によって異なりますが、火災保険ではおおむね、契約者または被保険者の「故意」や「重大な過失」、あるいは「法令違反」と認められるケースが該当します。
法令違反は法を破る行為(例えば、建物にわざと火をつけるなど)であり、比較的判断しやすいものです。しかし、故意や重大な過失かどうかの判断は難しく、個別のケースごとに判断されます。
過去の判例によると、鍵を長くかけずにいた勝手口から第三者が侵入して放火されたケース、放置していた空き家に放火されたケースなど、放火を予期できる状態であるにもかかわらず、放置していた場合に重大な過失と認定されています。
放火による損害を受けた場合、保険金はどのくらい受け取れる?
保険金には、「損害保険金」と「費用保険金」があります。
損害保険金は、損害を受けた保険の対象である建物や家財を損害発生前の状態に戻すための保険金で、契約した保険金額を上限に、実際の損害額受け取れます。
費用保険金は、損害を受けたことで間接的に必要となるさまざまな費用をサポートする保険金です。
損害保険金
放火による建物や家財への直接の損害は損害保険金で補償されます。
損害保険金を決定する基準には、「新価(再調達価額)」と「時価」があります。新価(再調達価額)は同等の建物や家財を再築、再購入するのに必要な金額、時価は購入時からの経過年数や使用による損耗を差し引いた金額です。
新価基準で火災保険に加入した場合、建物の損害額が再調達価格(再築、再購入に必要な金額をベースとした評価額)の一定割合(80%等)を超えた場合には全損扱いになり、設定した保険金額の全額を受け取れます。全損損害額が再調達価格の一定割合以下であれば、実際の損害額を受け取れます。
例えば新価(再調達価額)3,000万円を保険金額として火災保険に加入していれば、建物が全焼(または損害割合が一定以上)した場合は全損扱いで3,000万円、一部の焼失で修理費用が800万円と算出されると800万円の保険金が支払われます。
時価で保険金を設定すると、再調達価額3,000万円から経年劣化分の評価額が差し引かれた金額が保険金額となるため、万が一住宅が全焼しても再築に必要な3,000万円の補償は受けられません。
保険金だけで再築したり買い替えたりできるよう、保険金額は新価(再調達価額)を基準に設定するのが基本です。
費用保険金
費用保険金は損害保険金に上乗せする形で、臨時費用や残存物の解体・片付け費用、失火見舞い費用をサポートする保険金です。
費用保険金額は、一般的に「支払われる損害保険金額の10%(1事故につき100万円限度)」のように契約で定められています。例えば支払われる損害保険金額が500万円であれば、50万円が費用保険金として支払われます。
万が一の放火被害に備えるための対策

放火はいつ巻き込まれるかわからない恐ろしい犯罪です。完全に防ぐのは難しいかもしれませんが、放火されにくく、放火の被害を広げない環境を作ることは可能です。
そこで、放火被害への備えとしておすすめの対策を3つ紹介します。
放火されにくい環境を整える
まずは住宅の現状を点検して、放火犯に狙われやすいと思われる不安要素を取り除き、放火されにくい環境を整えることが大切です。
まずは住宅のまわりを整理整頓し、ごみ袋や段ボールなど燃えやすいものを置かないようにしましょう。マンションであっても、誰でも立ち入りやすい廊下や共用部には不用意に物を置かないように注意する必要があります。郵便物のたまったポストも狙われやすいため、気をつけましょう。
また、第三者の侵入を防ぐために玄関や勝手口はもちろん、物置や車庫などにも必ず鍵をかけましょう。
放火は夜間に起こるケースが多いので、外灯やセンサーライトで夜でも明るく、人目につきやすい環境を維持するのも有効です。
日頃の行動から放火を防ぐ
日頃の行動が、放火の被害にあいにくい環境作りにつながります。ごみ出しは収集当日の朝に行うだけでも、放火犯から狙われにくくなります。
また、外出するときは隣近所に声をかける、地域ぐるみで防火対策に取り組むなど、不審者が歩きにくい街作りも放火を防ぐ大きな後ろ盾になります。
近隣に空き家や空室があるときには、定期的な見回りが効果的です。
防災グッズを設置する
先に触れたとおり、放火および放火の疑いによる損害額はほかの火災よりも大きくなりやすいです。そのため、いざというときのために防災グッズを準備しておき、放火の被害拡大をできるだけ抑えましょう。
具体的には、消火器や住宅用火災警報器などを備える、車やバイク(二輪自動車)をお持ちの場合は防炎機能の施されたカバーを利用するなどが考えられます。
火災保険で万が一のリスクに備えながら放火対策も行うことが大切
放火による損害は、第三者の犯罪行為による場合、火災保険で補償されます。保険会社の免責事由に該当すると保険金は支払われませんが、ほとんどのケースで通常の火災と同じように補償されると考えて良いでしょう。
放火対策としては、放火されにくい、被害を広げにくい環境作りが大切です。さらに、新価(再調達価額)を基準に保険金を設定した火災保険に加入し、いざというときにも保険金で生活を立て直せる備えをしておきましょう。
監修者プロフィール

竹国 弘城
証券会社、生損保代理店での勤務を経て、ファイナンシャルプランナーとして独立。お金に関する相談や記事の執筆・監修を通じ、自分のお金の問題について自ら考え、行動できるようになってもらうためのサポートを行う。【保有資格】1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP®
よくあるご質問
被害にあわれた場合のご連絡先
通話料無料
年中無休、24時間365日ご連絡を受付けております。
- ※
-
IP電話をご利用の方で上記無料通話回線が繋がらない場合、海外からおかけになる場合は、お手数ですが以下の電話番号におかけください。
050-3786-1024(有料電話)
- ※
-
お電話をいただく際は、おかけ間違いのないよう、十分ご注意ください。