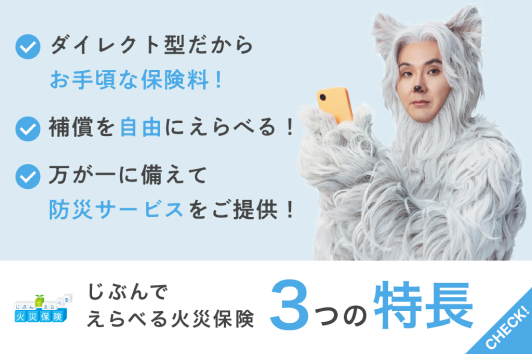火災保険ガイド
2024年10月に火災保険が値上げ!今回の改定の特徴や値上げ後の対策について解説
最終更新日:2025/3/27

度重なる自然災害などを背景に、火災保険の保険料は2024年10月に値上がりしました。直近10年間で5回目となります。損害保険料率を算出する公的機関である損害保険料率算出機構が算出した参考純率が大幅に引き上げられたことを受けて、今回は過去最大の値上げ幅となりました。
そのため、今後、火災保険の更新を迎えると保険料が高くなる可能性があります。この記事では、火災保険料の値上げの詳細や背景、そして値上げ後に取るべき対策について詳しく解説します。
1.火災保険料はどのぐらい値上がりした?
火災保険の保険料が値上がりした理由は、損害保険料率算出機構が算出する参考純率が2023年6月に改定され、全国平均で13.0%引き上げられたからです※。
この改定は、過去10年間で5回目の引き上げとなり、これまでで最大の引き上げ幅となりました。たとえば、2021年には10.9%の引き上げが行われましたが、今回の改定では、契約内容によってはさらに上回る値上げとなる場合があります。
参考純率の平均は引き上げとなりましたが、実際の保険料は所在地、建物構造、築年数などにより異なるため、一部地域では値下がりする可能性もあります。値上げ幅を正確に把握するためには、ご自身が契約している保険会社の改定情報を確認することが重要です。
- ※
-
平均水準であり、保険料がどのくらい値上がりするかは保険会社によって違います。また、参考純率の引き上げによって保険料も13.0%値上がりする訳ではありません。
1.1.引き上げされた参考純率とは
参考純率とは、損害保険料率算出機構が算出する純保険料率のことで、保険会社が自社の保険料を設定する際の基準となるものです。ただし、保険会社は参考純率をそのまま採用する義務はなく、自社の判断で保険料を設定するため、値上げ幅は保険会社ごとに異なります。
純保険料とは、契約者からお支払いいただいた保険料のうち、保険金の支払いに充てられる部分を指します。一方、付加保険料は、保険会社の運営コストなどに充てられる部分です。今回の改定では、参考純率の引き上げが純保険料の増加に影響し、それが契約者の負担増につながると考えられます。
1.2.過去の参考純率改定内容
参考純率の改定は、2014年以降これまでに4回実施されています。たとえば、2021年6月の改定では、全国平均で10.9%の引き上げが行われ、それにともない多くの保険会社で火災保険料が見直されました。今回も2023年6月の改定を受けて、各保険会社で2024年10月1日以降の契約について保険料の改定がされました。このように、参考純率の改定は保険料の直接的な値上げ要因となっています。
さらに、発表されている全国平均の引き上げ率は13%ですが、これは都道府県や建物の構造、築年数など契約条件によって異なる改定率を平均した数値です。そのため、所在地、建物構造、築年数などによって引き上げ幅が異なり、保険料にも反映されています。
たとえば、災害リスクが低い建物では保険料が値下がりしたり、据え置きになったりするケースもありますし、災害リスクが高い建物では大幅に値上がりしたケースもあります。
| 時期 | 参考純率の引き上げ率 (全国平均) |
その他の変更点 |
|---|---|---|
| 2014年7月 | 3.5% | 最長契約年数が36年から10年に変更 |
| 2018年6月 | 5.5% | |
| 2019年10月 | 4.9% | 築年数が浅い住宅(築浅住宅)に対する割引の導入 |
| 2021年6月 | 10.9% | 最長契約年数が10年から5年に変更 |
| 2023年6月 | 13.0% | 水災リスクの細分化 (2024年10月以降:保険会社も改定) |
- ※
-
築浅割引とは:保険始期日時点で築年数が10年未満である場合、建物の保険料を割り引きするもの
2.火災保険の改定の理由とは?
今回の火災保険改定にはいくつかの背景があります。以下で詳しく解説します。
2.1.災害が多発し火災保険の保険金支払いが急増
近年、台風や豪雨などの自然災害が多く発生しています。さらに、住宅の老朽化がすすんでいるうえに住宅の修繕費用も高騰しています。これらが火災保険金の支払額増加につながっている状況にあり、参考純率の引き上げの背景となっています。
2.2.水災料率における保険料負担の公平化
今回の改定では、水災料率が細分化されます。これまでは全国一律の保険料率でしたが、地域によって、浸水や土砂崩れなどの水災リスクには差があり、公平性に課題がありました。
また、ハザードマップの情報の充実により、水災リスクの低い地域に住む契約者が水災補償を外す傾向にあり、さらなる水災料率の引き上げを避けられないことから細分化されることとなったのです。リスクの低い地域と、大型台風や豪雨の被害が頻発するリスクの高い地域に応じて、保険料がもっとも安い「1等地」からもっとも高い「5等地」までの5区分に分かれます。
2.2.1.水災リスクが5区分に細分化されたことによる影響
水災料率の細分化により、地域ごとにリスクを反映した水災料率が設定されます。たとえば、1等地では水災料率の引き上げ幅が少なかったり、地域や構造によっては引き下げられたりする一方で、5等地では大幅に引き上げられました。水災料率の改定によって、今後改定される火災保険料も地域によって格差が生じるため、同じ都道府県だとしても、値下がりする地域と、大きく値上がりする地域が出てくるでしょう。
2.2.2.水災リスクによる改定率の例
ここでは例として、保険金額が建物2,000万円、家財1,000万円、建物が築10年以上の場合の改定率をみてみましょう。改定率は、所在地、建物構造、築年数や水災リスクによって異なります。なお、表にある「M構造」とはコンクリート造のマンションなど、「T構造」とは鉄骨造の一戸建て、「H構造」とはM構造やT構造に該当しない木造の一戸建てを指しています。
たとえば、東京都や大阪府では、水災リスクの高い地域でのM構造の建物の場合、約20%から26%の値上げが見込まれています。建物構造や築年数に応じてさらに差が生じるため、契約内容の見直しが必要です。
【M構造】
| 都道府県 | 水災等地別の改定率 (1等地~5等地) |
|
|---|---|---|
| 三大都市 | 東京都 | +4.3% ~ +20.2% |
| 大阪府 | +11.6% ~ +25.9% | |
| 愛知県 | +7.6% ~ +23.6% | |
| 改定が最大の地域 | 宮崎県 | +20.4% ~ +29.9% |
| 改定が最小の地域 | 香川県 | +3.7% ~ +21.3% |
【T構造】
| 都道府県 | 水災等地別の改定率 (1等地~5等地) |
|
|---|---|---|
| 三大都市 | 東京都 | +5.2% ~ +26.8% |
| 大阪府 | +14.9% ~ +32.6% | |
| 愛知県 | +7.2% ~ +27.2% | |
| 改定が最大の地域 | 群馬県 | +16.9% ~ +33.6% |
| 改定が最小の地域 | 山形県 | +3.7% ~ +18.4% |
【H構造】
| 都道府県 | 水災等地別の改定率 (1等地~5等地) |
|
|---|---|---|
| 三大都市 | 東京都 | -1.3% ~ +19.0% |
| 大阪府 | +11.4% ~ +27.1% | |
| 愛知県 | +1.9% ~ +20.6% | |
| 改定が最大の地域 | 群馬県 | +12.3% ~ +27.7% |
| 改定が最小の地域 | 東京都 | -1.3% ~ +19.0% |
- ※
-
参照:損害保険料率算出機構 火災保険参考純率 改定のご案内
3.値上げ後に見直しが必要な人はどんな人?
今回の水災料率改定により、次回の更新時にかなり保険料が値上がりする可能性がある方もいます。値上げの影響を受ける可能性が高い方と、値上げ後に取るべき対策を解説します。
3.1.災害リスクの高い地域に住んでいる方
災害リスクが高い地域に住んでいる場合、水災補償や特約の取捨選択を行うことで保険料を抑えることができます。まずは、お住まいの自治体が作成しているハザードマップを確認し、災害リスクを客観的に知ることが大切です。
特約を取捨選択する際は、生活基盤を大きく揺るがしかねない風水災や地震への補償を優先させ、たとえば携行品損害補償特約などはご自身にとって必要な補償なのか、今一度よく考えることをおすすめします。
また、個人賠償責任特約などは、火災保険以外の自動車保険で加入していたり、お持ちのクレジットカードに付帯されていることもあり得ます。一度確認をし、重複している場合は更新時に外すことも検討しましょう。
3.2.1年契約で火災保険を契約している方
保険期間を長期契約に変更することで、保険料を抑えられる場合があります。 たとえば、2年以上の契約では割引が適用され、トータルの支払い額を抑えられるのが一般的でしょう。
たとえば以下の条件で1年契約と2年契約を比べてみました。
[契約条件]
東京都・M構造
保険金額(建物):2000万円
保険金額(家財):1930万円
地震保険:なし
風災免責金額:0円
水災等地:5
その他補償:なし
建築年月:2009年3月
補償開始日:2025年3月
支払方法:一括
この内容で試算したところ、1年契約の保険料は26,340円、2年契約の保険料は50,520円となり、2年契約の方が割安であることがわかります。
こちらの記事で火災保険の長期契約に関して詳しくお伝えしていますのでぜひ参考にしてください。
4.値上げ後の対策ポイント

値上げ後に取るべき具体的な対策を説明します。
4.1.保険会社をきちんと比較する
火災保険の保険料は保険会社ごとに異なるため、複数の見積りを比較することが重要です。見積りサービスを利用することで、自分にあった保険を見つけやすくなります。ただし、火災保険は、補償の組み合わせの自由度に保険会社ごとに大きな差があります。そのため見積りサービスでは、まったく同じ補償内容で保険料を比べることは難しくなるため注意が必要です。
SOMPOダイレクトの「じぶんでえらべる火災保険」は、補償内容を柔軟に設定できるため、必要な補償だけを選び保険料を抑えることも可能です。
4.2.免責金額を検討する
火災保険の契約時に、事故が発生した際に自己負担する「免責金額」を設定すると保険料は変動し、高めに設定するほど、保険料を抑えることができます。
たとえば、免責金額を10万円とすると、10万円以下の損害では保険金を受け取ることはできませんし、50万円の損害が生じた場合は、40万円の保険金を受け取ることとなります。いくらくらいなら自己負担できるか考えて、設定すると良いでしょう。
ただし、免責金額を高く設定すると、万が一事故が発生した際の自己負担金額が大きくなることにはご注意ください。
5.火災保険の値上げを機に一度見直しをしよう
火災保険料の値上げは、契約内容を見直す良い機会です。補償内容や特約を再確認し自分に最適な保険を選ぶことで、保険料負担を軽減できます。特に災害リスクが高い地域にお住まいの方は、今回の改定内容をふまえたうえで契約内容を見直してみてはいかがでしょうか。
監修者プロフィール

鈴木 さや子(すずき さやこ)
株式会社ライフヴェーラ代表
生活に役立つお金の知識を、企業講演、セミナーやメディアを通じて情報発信。専門は資産形成・教育費・保険・マネー&キャリア教育。損害保険会社勤務を経て現職。保険や金融商品を一切直接販売せず、毎日を過ごすためのお金・キャリアの情報を発信している。近著に『資産形成の超正解100』(朝日新聞出版)・『18歳からはじめる投資の学校(翔泳社)』。
資格情報: CFP®認定者、1級FP技能士、DCプランナー1級・キャリアコンサルタント(国家資格)
よくあるご質問
被害にあわれた場合のご連絡先
通話料無料
年中無休、24時間365日ご連絡を受付けております。
- ※
-
IP電話をご利用の方で上記無料通話回線が繋がらない場合、海外からおかけになる場合は、お手数ですが以下の電話番号におかけください。
050-3786-1024(有料電話)
- ※
-
お電話をいただく際は、おかけ間違いのないよう、十分ご注意ください。