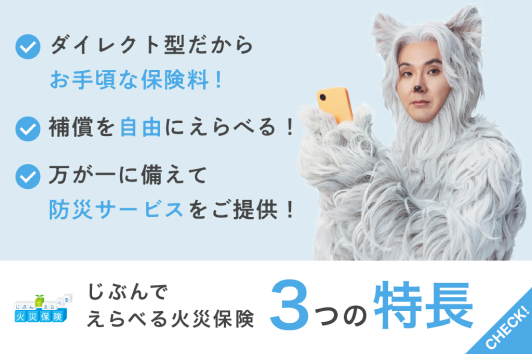火災保険ガイド
引越し時の火災保険はどうしたらいい?状況別の手続き方法や見直すべきポイントを紹介
最終更新日:2025/3/27

火災保険といえば、入居する新たな住まいに対して加入を検討するだけのものと思っていませんか?今の住まいから引越しする際に、これまでの火災保険を続けることができれば便利ですよね。ここでは、引越しの状況に応じた火災保険の取扱いについて、手続き方法や見直しポイントを解説します。
1.引越しする場合は火災保険の手続きも必要
引越しする物件が決まると、新しい家具や電化製品を探すなど、楽しみも多いもの。しかし忘れてはいけないのは、自分の住まいを災害から守る火災保険です。転居したら新しい契約をしなければいけないと考えがちですが、引越しの状況や今加入している火災保険の契約内容によっては転居前の契約を引き継ぐことも可能です。引き継ぐ際にはさまざまな手続きが必要になりますし、転居のパターンによっては解約し再契約が必要となることもあるので注意が必要です。
2.パターン別:火災保険の手続き方法を紹介
転居のパターン別に、火災保険の手続き方法を見ていきましょう。
2.1.賃貸から賃貸に引越しする場合
賃貸に住む場合、建物自体の火災保険は家主が加入しますので、借主が契約するのは家財を対象とした火災保険となり、保険期間2年での契約が一般的です。この家財を対象とした火災保険は、転居先の賃貸物件でも継続できる場合があります。
つまり、
①もとの火災保険を解約し、転居先で火災保険を新たに契約する
②現在契約している火災保険を転居後も継続する
という2つの選択肢があります。ただし、②の継続をする場合、異動手続きが必要となります。また、保険料が再計算されるため、追加の保険料が必要となる場合があります。①の解約の際は、残り期間に応じて保険料が戻ってくる場合がありますので、忘れずに確認しましょう。詳しくは後述します。
なお、賃貸物件によっては、指定の火災保険でしか契約できない場合もあり、その場合は①を選ぶことになります。
2.2.賃貸から持ち家に引越しする場合
賃貸から持ち家に引越しする場合、火災保険は新たに契約が必要です。なぜなら賃貸の場合、火災保険では家財のみ対象としますが、持ち家になると、ご自身で火災などのリスクに備える必要が出てくるため、建物も対象に含めることが望ましいからです。
また、マイホームを購入するために住宅ローンを組む場合は、ローンを組んだ金融機関から建物を対象とした火災保険への加入を求められることが一般的です。賃貸から持ち家への引越しする際は、現在の火災保険の解約と、家財と建物を対象とした新たな火災保険の契約を忘れないようにしましょう。
2.3.持ち家から賃貸に引越しする場合
持ち家から賃貸に引越しする場合、現在の火災保険を解約し、家財を対象とする火災保険に新たに加入するのが一般的です。ただし、家財の火災保険は変更手続きを行うことで継続できる場合もあるので、賃貸の契約時に火災保険に加入している旨を伝え、継続できないか確認をすると良いでしょう。
なお、持ち家を手放さずに保有する場合は現在の火災保険を継続したまま、賃貸物件で新たな火災保険に加入しますが、持ち家が空き家になる場合は、加入を継続できるかどうか保険会社によっても異なるため、注意が必要です。
2.4.持ち家から持ち家に引越しする場合
持ち家から別の持ち家に引越しする場合、現在の火災保険を解約し、新しい家で新たな火災保険に加入するのが一般的です。ただし、変更手続きによって現在の火災保険を継続できる場合があります。その場合、建物の構造や床面積の違いによって保険料の過不足が生じることがあるので注意しましょう。
なお、持ち家を手放さずに保有する場合は現在の火災保険を継続したまま、新たな持ち家で火災保険に加入しますが、もとの持ち家が空き家になる場合は、加入を継続できるかの確認および、継続できる場合も契約の変更手続きが必要となるためその点も注意が必要です。
3.途中解約した場合は解約返れい金がでる

現在の火災保険は最長で5年の契約が可能ですが、以前は10年以上の契約が可能な時期もありました。5年や10年といった長期の契約において、保険料を一括払や年払で支払っている場合、契約期間の途中で解約すると、未経過分の保険料のうち、所定の方法で算出された金額が解約返れい金として戻ってきます。
途中解約に対する違約金はありませんので、いつでも解約は可能です。また、新たな住まいに引越しをする際、もとの住まいで加入していた火災保険の解約手続きを忘れてしまうと、保険料を二重に支払う状況となるため注意しましょう。
3.1.火災保険解約時の流れ
ステップ1:契約している保険会社または代理店に連絡をする
ステップ2:解約に必要となる書類を送付する
ステップ3:解約完了の通知を受け取る
ステップ4:受理から1週間~10日程度で解約返れい金が振り込まれる
3.2.解約返れい金の計算方法
火災保険を解約する際に受け取ることができる解約返れい金の金額は、契約の期間がどのくらい残っているかに応じて決まります。
長期年払や1年一括払の場合は未経過月分が戻りますが、長期一括払契約の場合は、保険会社ごとに定められている未経過料率を使って算出されます。たとえば、5年契約の火災保険を2年8か月で解約した場合、残りの2年4か月分の保険料が返ってきますが、その計算に未経過料率が使われます。
計算式は次のとおりです。
解約返れい金=長期一括払保険料×未経過料率
なお、未経過料率は月単位で設定されていますが、契約後1か月未満で解約した場合であっても契約時にかかっているコストなどを差し引くため、支払った保険料が100%返ってくることはありません。また、契約の残り期間が1か月未満の場合には端数として切り捨てられ、解約返れい金は戻りません。
解約返れい金についてもっと詳しく知りたい方はこちら
4.引越しにともなう火災保険の見直しポイント
引越しの際は、物件選びから引越し業者の手配、新しい家具や家電製品の購入のほか、転居に伴うさまざまな行政の手続きやお子さまがいる場合は転校手続きなどが必要となります。必要な手続きを見逃さないためにも、ぜひ下記に記載している「引越チェックリスト」をご活用ください。
4.1.補償範囲の再確認
火災保険は火事だけではなく自然災害を広く補償するため、転居先にどのような災害リスクがあるか、ハザードマップなどで確認することが大切です。ハザードマップとは、国や都道府県、市町村が作成している「自然災害による被害の軽減や防災対策に使用する地図」で、被災が想定される区域や、避難場所といった防災関連施設の位置などが表示されているものです。
たとえば、ハザードマップ上で「浸水や土砂災害」などの被害が心配されることがわかれば、水災補償は欠かせません。新たに契約する際に水災の補償をつけることはもちろん、契約している火災保険を継続する場合にも補償内容の見直しが必須です。
各種の特約は、契約途中で追加できるものもあれば、契約自体を新たに切り替えなければならないケースもあるので、契約している保険会社への確認を忘れないようにしましょう。
4.2.保険期間の適切な設定
火災保険は最長5年間の契約が可能で、保険期間が長いほど1年あたりの保険料は割安になります。ただし、これから先のご自身の住まいを考えたとき、定期的に引越しの予定がある場合は、火災保険も臨機応変に見直せるよう1年契約にする方が良いでしょう。逆に、当面は引越し予定がないのであれば、長期契約にすることで、保険料負担を抑えることを考えましょう。いずれにしても、状況に応じて保険期間を設定することが大切です。
4.3.地震保険の必要性
地震が多いことで知られる日本では、震度1以上の有感地震が概ね年間2,000回程度発生しています。
大規模な地震が発生すると、建物の倒壊や火災、地震による津波などの被害に見舞われる可能性がありますが、これらの損害は火災保険の補償対象外となっています。地震に備えるために必要な「地震保険」は、火災保険とセットで契約する必要があるため、地震の危険度が高い地域や、津波の影響が予想される地域お住まいの方は、火災保険を見直す際に、地震保険への加入を検討しましょう。
4.4.補償の空白期間を作らない
引越しの際にやるべきことは多いため、火災保険の切替えを忘れたり、後回しにしたりしがちです。しかし、どんな時でも火災や自然災害による被害を受ける可能性があります。火災保険の見直しや異動の手続きを忘れているときに、思いがけず被害を受けてしまう状況になると、一切補償されないおそれがあります。ほかの保険会社に乗り換える場合も、同じ保険会社での再契約をする場合にも、補償の空白期間を作らないように細心の注意を払いましょう。
5.引越し状況にあわせて火災保険の見直しも忘れずに
引越しをする時は、火災保険の見直しタイミングでもあります。新たに契約する方はもちろん、これまで加入していた火災保険を引き継ぐ方も、引越し先の水災リスクを調べたり地震保険の必要性などを検討し、その環境に必要な補償にあわせて適切な内容に見直すことが大切です。
そして見直しの際には、現在契約中の保険会社だけなく、さまざまな保険会社でシミュレーションを行い、自分にあった補償内容における保険料の違いを確認することをおすすめします。
こちらから、簡単に保険料をシミュレーションすることができるので、ぜひご活用ください。
監修者プロフィール

鈴木 さや子(すずき さやこ)
株式会社ライフヴェーラ代表
生活に役立つお金の知識を、企業講演、セミナーやメディアを通じて情報発信。専門は資産形成・教育費・保険・マネー&キャリア教育。損害保険会社勤務を経て現職。保険や金融商品を一切直接販売せず、毎日を過ごすためのお金・キャリアの情報を発信している。近著に『資産形成の超正解100』(朝日新聞出版)・『18歳からはじめる投資の学校(翔泳社)』。
資格情報: CFP®認定者、1級FP技能士、DCプランナー1級・キャリアコンサルタント(国家資格)
よくあるご質問
被害にあわれた場合のご連絡先
通話料無料
年中無休、24時間365日ご連絡を受付けております。
- ※
-
IP電話をご利用の方で上記無料通話回線が繋がらない場合、海外からおかけになる場合は、お手数ですが以下の電話番号におかけください。
050-3786-1024(有料電話)
- ※
-
お電話をいただく際は、おかけ間違いのないよう、十分ご注意ください。